ますます誰得感が強くなって来た「私の文章修行シリーズ」。アメブロ過疎化のせいだけでなく、アクセス数は低迷したままだが、気にしないで「その3」を書く。
「その1」で「タイトル」と「書き出し」、「その2」で文中で使う「言葉」について述べた。その流れで「その3」では「文」そのものについて書きたい。ということは、
「あとは段落と段落のつながり、文章全体の成り立ち、と続くんだろうな」
と読書諸賢は予想するかも知れないが、その通りである。← 何のひねりもないんかーい!
正しい文を書くにあたってしばしば言われることは、
「文章を書いた後、ひとつひとつの文の『てにをは』を見直そう」
「文の主語と述語が対応しているか、チェックしよう」
ということである。言うまでもないだろうが、「てにをは」とは単語に付く「は」「が」「に」「へ」「を」「も」「と」「の」「て」「で」「や」など助詞と呼ばれるものを指している。これらが正しくないと、
「ひとつひとつ文は『てにをは』の見直すですね♪」
みたく日本語を学び始めた人の会話文のようになってしまう。逆に言えば、日本語を使い慣れている人の会話はこのようにはならない。ふだんは自然な会話ができるのに、文を書くとたちまち変な文になってしまうなら、その原因は何か。それはひとえに文を書くスピードが話をするスピードよりも遅いことにある。← これ、ワタクシの新説だからメモしてね♡
![]()
多くの人がそうだろうが、文を作るスピードの順番は、
『 (1) 頭の中で考え出す > (2) 話として口に出す > (3) 文として書く』
である。(3) をさらに順番付けすると、
『 (3-1) パソコンでタイプ入力する > (3-2) スマホでフリック入力する > (3-3) 手書きする』
となることが多いと思う。人によってはパソコンとスマホの順番が入れ替わるかも知れない。とにかく、「 (2) 会話」では正しい日本語を話している人が「 (3) 文を書く」とおかしくなってしまうことはよくある。
正しい文を書く方法として、学校の先生は、
「文章を書いたら、その後で見直しをしましょう」
とのたまうが、
「んなこといちいちやってられっかっ!」
というのが普通の高校生、反抗的なヤンキー男子高生、先生にもてあそばれて恨みを持っている女子高生である。でも大丈夫。そういう後ろ暗い過去を持ったJKでも、LINEでは見直しなしで正しい文を送れる大人女子になる。
![]()
LINEで自然な会話が出来るのに、ブログでは「てにをは」がおかしくなるのはなぜだろうか。もうお分かりだろう。「 (3) 文字入力するスピード」が「 (2) 話をするスピード」、「 (1) 頭で考えるスピード」よりも遅いことが原因である。ということは正しい文を書くには、女子高生をもてあそぶ高校教師の言うことなど聞かず、文字を入力するスピードを速くすることである。つまり、
『「 (3) 文字入力のスピード」を「 (2) 話をするスピード」と同じくらいに上げること、さらに 「 (1) 頭で考え出すスピード」に近づけること』
が「てにをは」が正しい文、自然な文につながるのである。文字入力をスピードアップすれば「てにをは」だけでなく、主語と述語の一致、主語の省略、受け身の文にするかどうか、「なので」や「ていうのは」のような文のつながりの問題などが一挙に解決する。
結局のところ、長い文章 (ブログやスピーチ) が書ける人というのは、文字入力のスピードが速いだけのことである。何も文章力が優れているなどとホメちぎるまででもない。マシンガントークをする女子が文字入力のスピードが速くなるように練習すれば、むちゃくちゃ長いブログ記事が書けるようになる。かく言うワタクシも「 (3-1) パソコンのタイプ入力スピード」が「 (1) 頭で考えるスピード」に近いだけのことである。
ちなみに、私にスマホやガラケーでメールを書かせると、文章に現れる性格が借りてきた猫のように変わって見えるらしい。
「トシさん、調子悪い? なんだか頭が回ってないんじゃない?」
ということになる。頭が回っていないのではなく、パソコンを打つ手が猫の手になっただけのことである。そりゃ、猫の脳みそに見えるはずである。
![]()
スマホ入力やパソコン入力を鍛える弊害があるとすれば、妙に長い文章を書いてしまうということがある。よそ様のブログに長文のコメントしてしまう、メールの返事が長すぎる、ブログにページ番号を入れないと読めないなど。けれど、書いている時間は短いから本人に罪の意識はまったくない。
特に名を秘すぬ○姫は中国で初等教育を受けたせいか、私の長い日本語コメントにダメ出しをし、コメントは五七五七七の短歌形式にするよう最後通告を突きつけて来た。たとえば、
★ ぬ○姫や ドイツの空に 何、想う
帰って来なよ ブログにだけでも…
字余り、お粗末。
あ、リブログしたら、名前出ちゃったw
ほら、長くなった。思いつくままにパソコンでマシンガン入力すると一気にここまで書いてしまう。あと、「文」について「てにをは」以外で気をつけることと言えば、「文の流れ」だろう。ひとつひとつの文に続いて、文の並びについての注意である。前の文とのつながりで「それ」「そのこと」などが何を指すのか分からないとか、後の文がなぜ前の文に続いているのか分からないということを避ける。さらには文章をテンポ良く読んでもらうにはどうすれば良いかということである。
これらの大半は先に書いた「文字入力のスピードを上げること」で解決する。あとは自分の文体という個性が出せるかどうかである。このことについてワタクシには密かに敬愛する文章作成の師匠がいる。東海林さだお氏である。氏は漫画家として有名だが、同時に「あれも食いたい、これも食いたい」などのエッセーで世間の評判が高い (1995年 講談社エッセイ賞、2000年 紫綬褒章、2011年 旭日小授賞、202X年 ノーベル文学賞 (予定) )。
東海林さだお氏のエッセーを抜粋しよう。
まずラーメンの全容をじっくりと眺め、ラーメンの表面を軽く箸でひと撫で。チャーシューを右上のスープに軽く沈め、心の中で「後でね…」と詫びてから麺を一箸。次にシナチクを一本口中に投じ、さらに麺をすする。そして、シナチクを一本。続いてスープを3口すすり、軽くほーっとため息をついてからようやくチャーシューへ。
何と流麗な文体であろう。チャーシューに対して「後でね…」と詫びるおかしさ。「全容」「口中」といった難しい熟語と内容のギャップ。ときに文を区切り、ときに長い文を交えるテンポ良さ。伊丹十三監督の映画「たんぽぽ」の台詞に使われるのも納得である。← 山崎努さんのセリフね♪
![]()
もうひとつ、東海林さだお氏のエッセーを中略しながら抜粋する。
ぼくはその日、すっかりおばあさんになってしまった。その日というのは、タクアンを漬けた日のことである。いい具合にしなびて、渋茶色してぐったりしている大根の束を見ているうちに、「タクアンを漬けたい」という欲求がムラムラとわいてきたのである。みずみずしく白い陶器のような生の大根と、水気を失ってシワシワ、ヘナヘナの干し大根。ミス○○と、元ミス○○の違い。
意表を突く「書き出し」の秀逸さ。ムラムラと湧く欲求から、ミス○○と元ミス○○を思い起こす独特の目線。着眼点と発想が素晴らしく、流れる文体で稀有な着想を読者に読ませる筆力は見事と言うほかない。
多くのブロガーは何かを思いついて記事を書き始める。せっかく思いついたその何かを文章にして残したい、誰かに伝えたいと思うのが人の世の常である。それを読んでもらえる、聞いてもらえるようにするには場数を踏むというありきたりな結論になるだろう。たくさん書いて、たくさんしゃべるうちに面白いブログが書けたり、楽しい会話が出来るようになる。ただ、
「練習すべきことは文字入力のスピードアップである」
というのがワタクシの意見である。
田舎育ちの無口な純情少年は街に出てニヒルで陰のあるイケメン好青年になり、やがて多くしゃべるようになると面白いだけのモテない社会人になる。それが私である。← ダメじゃんw ← いいじゃん、楽しければ♪
![]()
「その1」で「タイトル」と「書き出し」、「その2」で文中で使う「言葉」について述べた。その流れで「その3」では「文」そのものについて書きたい。ということは、
「あとは段落と段落のつながり、文章全体の成り立ち、と続くんだろうな」
と読書諸賢は予想するかも知れないが、その通りである。← 何のひねりもないんかーい!
正しい文を書くにあたってしばしば言われることは、
「文章を書いた後、ひとつひとつの文の『てにをは』を見直そう」
「文の主語と述語が対応しているか、チェックしよう」
ということである。言うまでもないだろうが、「てにをは」とは単語に付く「は」「が」「に」「へ」「を」「も」「と」「の」「て」「で」「や」など助詞と呼ばれるものを指している。これらが正しくないと、
「ひとつひとつ文は『てにをは』の見直すですね♪」
みたく日本語を学び始めた人の会話文のようになってしまう。逆に言えば、日本語を使い慣れている人の会話はこのようにはならない。ふだんは自然な会話ができるのに、文を書くとたちまち変な文になってしまうなら、その原因は何か。それはひとえに文を書くスピードが話をするスピードよりも遅いことにある。← これ、ワタクシの新説だからメモしてね♡
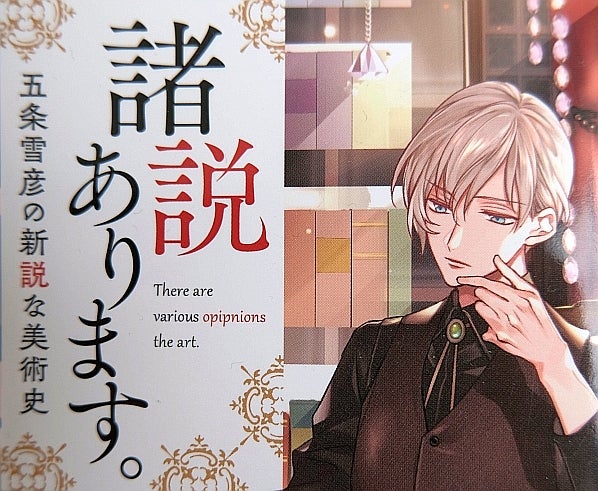
多くの人がそうだろうが、文を作るスピードの順番は、
『 (1) 頭の中で考え出す > (2) 話として口に出す > (3) 文として書く』
である。(3) をさらに順番付けすると、
『 (3-1) パソコンでタイプ入力する > (3-2) スマホでフリック入力する > (3-3) 手書きする』
となることが多いと思う。人によってはパソコンとスマホの順番が入れ替わるかも知れない。とにかく、「 (2) 会話」では正しい日本語を話している人が「 (3) 文を書く」とおかしくなってしまうことはよくある。
正しい文を書く方法として、学校の先生は、
「文章を書いたら、その後で見直しをしましょう」
とのたまうが、
「んなこといちいちやってられっかっ!」
というのが普通の高校生、反抗的なヤンキー男子高生、先生にもてあそばれて恨みを持っている女子高生である。でも大丈夫。そういう後ろ暗い過去を持ったJKでも、LINEでは見直しなしで正しい文を送れる大人女子になる。

LINEで自然な会話が出来るのに、ブログでは「てにをは」がおかしくなるのはなぜだろうか。もうお分かりだろう。「 (3) 文字入力するスピード」が「 (2) 話をするスピード」、「 (1) 頭で考えるスピード」よりも遅いことが原因である。ということは正しい文を書くには、女子高生をもてあそぶ高校教師の言うことなど聞かず、文字を入力するスピードを速くすることである。つまり、
『「 (3) 文字入力のスピード」を「 (2) 話をするスピード」と同じくらいに上げること、さらに 「 (1) 頭で考え出すスピード」に近づけること』
が「てにをは」が正しい文、自然な文につながるのである。文字入力をスピードアップすれば「てにをは」だけでなく、主語と述語の一致、主語の省略、受け身の文にするかどうか、「なので」や「ていうのは」のような文のつながりの問題などが一挙に解決する。
結局のところ、長い文章 (ブログやスピーチ) が書ける人というのは、文字入力のスピードが速いだけのことである。何も文章力が優れているなどとホメちぎるまででもない。マシンガントークをする女子が文字入力のスピードが速くなるように練習すれば、むちゃくちゃ長いブログ記事が書けるようになる。かく言うワタクシも「 (3-1) パソコンのタイプ入力スピード」が「 (1) 頭で考えるスピード」に近いだけのことである。
ちなみに、私にスマホやガラケーでメールを書かせると、文章に現れる性格が借りてきた猫のように変わって見えるらしい。
「トシさん、調子悪い? なんだか頭が回ってないんじゃない?」
ということになる。頭が回っていないのではなく、パソコンを打つ手が猫の手になっただけのことである。そりゃ、猫の脳みそに見えるはずである。

スマホ入力やパソコン入力を鍛える弊害があるとすれば、妙に長い文章を書いてしまうということがある。よそ様のブログに長文のコメントしてしまう、メールの返事が長すぎる、ブログにページ番号を入れないと読めないなど。けれど、書いている時間は短いから本人に罪の意識はまったくない。
特に名を秘すぬ○姫は中国で初等教育を受けたせいか、私の長い日本語コメントにダメ出しをし、コメントは五七五七七の短歌形式にするよう最後通告を突きつけて来た。たとえば、
★ ぬ○姫や ドイツの空に 何、想う
帰って来なよ ブログにだけでも…
字余り、お粗末。
あ、リブログしたら、名前出ちゃったw
ほら、長くなった。思いつくままにパソコンでマシンガン入力すると一気にここまで書いてしまう。あと、「文」について「てにをは」以外で気をつけることと言えば、「文の流れ」だろう。ひとつひとつの文に続いて、文の並びについての注意である。前の文とのつながりで「それ」「そのこと」などが何を指すのか分からないとか、後の文がなぜ前の文に続いているのか分からないということを避ける。さらには文章をテンポ良く読んでもらうにはどうすれば良いかということである。
これらの大半は先に書いた「文字入力のスピードを上げること」で解決する。あとは自分の文体という個性が出せるかどうかである。このことについてワタクシには密かに敬愛する文章作成の師匠がいる。東海林さだお氏である。氏は漫画家として有名だが、同時に「あれも食いたい、これも食いたい」などのエッセーで世間の評判が高い (1995年 講談社エッセイ賞、2000年 紫綬褒章、2011年 旭日小授賞、202X年 ノーベル文学賞 (予定) )。
東海林さだお氏のエッセーを抜粋しよう。
まずラーメンの全容をじっくりと眺め、ラーメンの表面を軽く箸でひと撫で。チャーシューを右上のスープに軽く沈め、心の中で「後でね…」と詫びてから麺を一箸。次にシナチクを一本口中に投じ、さらに麺をすする。そして、シナチクを一本。続いてスープを3口すすり、軽くほーっとため息をついてからようやくチャーシューへ。
何と流麗な文体であろう。チャーシューに対して「後でね…」と詫びるおかしさ。「全容」「口中」といった難しい熟語と内容のギャップ。ときに文を区切り、ときに長い文を交えるテンポ良さ。伊丹十三監督の映画「たんぽぽ」の台詞に使われるのも納得である。← 山崎努さんのセリフね♪

もうひとつ、東海林さだお氏のエッセーを中略しながら抜粋する。
ぼくはその日、すっかりおばあさんになってしまった。その日というのは、タクアンを漬けた日のことである。いい具合にしなびて、渋茶色してぐったりしている大根の束を見ているうちに、「タクアンを漬けたい」という欲求がムラムラとわいてきたのである。みずみずしく白い陶器のような生の大根と、水気を失ってシワシワ、ヘナヘナの干し大根。ミス○○と、元ミス○○の違い。
意表を突く「書き出し」の秀逸さ。ムラムラと湧く欲求から、ミス○○と元ミス○○を思い起こす独特の目線。着眼点と発想が素晴らしく、流れる文体で稀有な着想を読者に読ませる筆力は見事と言うほかない。
多くのブロガーは何かを思いついて記事を書き始める。せっかく思いついたその何かを文章にして残したい、誰かに伝えたいと思うのが人の世の常である。それを読んでもらえる、聞いてもらえるようにするには場数を踏むというありきたりな結論になるだろう。たくさん書いて、たくさんしゃべるうちに面白いブログが書けたり、楽しい会話が出来るようになる。ただ、
「練習すべきことは文字入力のスピードアップである」
というのがワタクシの意見である。
田舎育ちの無口な純情少年は街に出てニヒルで陰のあるイケメン好青年になり、やがて多くしゃべるようになると面白いだけのモテない社会人になる。それが私である。← ダメじゃんw ← いいじゃん、楽しければ♪
